快眠のすすめカテゴリ: 快眠のすすめ
寒くても朝までぐっすり快適に眠る為に
さて、今回は・・・、
「冬の快適な睡眠方法」
について解説します!
冬になるとどうしてもうまく眠れない、眠りが浅くなるという方が多いのではないのでしょうか。
なかなか寝付けない、夜中に目が覚める、トイレの回数が増える、朝布団から出られないなどと、誰もが経験があるかと思います。 では、何故このような症状が起こるのか、原因と対策を説明します。
■眠れなくなる原因
① 手足の冷え
うまく眠れない原因の一つとして、寝室の温度や湿度の影響があります。
人は体温を少しずつ下げながら眠ることで深い睡眠を得ています。しかし、部屋が寒く、手足が冷えた状態だと体温を放出できず、寝つきが悪くなります。
② 就寝前の生活の乱れ
就寝前の何気ない行動にも、睡眠を妨げるものが多くあります。例えば、寝る直前の食事・アルコールの過剰摂取・カフェインの摂取・ブルーライトなどが挙げられます。快適な睡眠を得るためには、徹底してこのような悪影響の物を排除する必要があります。
また、脳が興奮した状態で布団に入ると睡眠の質を下げる原因になります。
③ 冬の気候
すっきりと起床するには朝一番に朝日を浴びること、と聞いたことはありませんか。
冬は夏に比べて、日が昇るのが遅くなるため、いつもと同じ時間に朝日を浴びることが物理的に難しくなります。また、日が落ちるのも早い為、夜の時間が長くなり、就寝時間も遅くなりがちです。
そんな冬の気候そのものが睡眠時間の確保を難しくしており、快適な睡眠を妨げる原因になっているのです。
■対策方法
対策① 最適な温度、湿度
室内の温度はエアコンなどで調節し、20℃前後の設定にしてください。
最適な状態を維持するために、起床までエアコンはつけたままが理想です。つけたままにしたくない人は、就寝30分前~2時間運転した後にOFF、起床1時間前にONになるように設定するのがオススメです。冬は寒いだけでなく、乾燥しやすい季節です。乾燥するとノドや鼻の粘膜が傷みやすくなる為、濡れたタオルを置いたり、加湿器を設置するなど、室内の湿度を50%前後に調整するとよいでしょう。
また、布団の中の温度・湿度も大切です。布団の中の温度、湿度を「寝床内気候」といい、布団の中の快適な温度は33℃前後、湿度は50%前後と言われています。
自分に合った寝具を選び、正しい温度・湿度で寝るようにしましょう。
対策② 入浴方法
寝る前に若干ぬるめのお風呂に入りましょう。40℃以下の熱すぎない温度が最適です。
就寝の1~2時間前に入浴を済ませるのが良いと言われています。お風呂で温まった体温が眠りにつくまでに少しずつ低下していき、心地よい入眠が期待できます。
ぬるめのお風呂は副交感神経を優位にし、高ぶった気分を鎮めて眠りへと誘ってくれます。
対策③ 食事は就寝2時間前までに
睡眠の質を高めるには食事をするタイミングも重要です。
寝る直前に食事をすると、消化・吸収のために脳と内臓が働いてしまい、睡眠の質が低下してしまいます。
寝る直前の食事は翌日の胃もたれの原因になります。また、寝る直前に食事をすることが習慣化すると肥満の原因にもなります。食事は就寝する2時間前には済ませるようにしましょう。
対策④ 起床時にライトをつける
人間の体内時計は明るさと暗さに直結しています。朝一番に太陽の光を浴びられない場合は、明るい光で代用してみましょう。日の出を再現するように調光しながら、光が点灯し始める照明器具もありますよ。
対策⑤ いつもと同じ時間に寝る
秋の夜長という言葉にもあるように、秋や冬はついつい夜更かしをしがちです。しかし、快適な睡眠を取るためには、いつもと同じ時間に寝て、睡眠時間を確保することが大切です。
但し、眠くもないのに無理をして布団に入ると、寝ることを意識しすぎてかえって頭が休まりません。眠くなってから布団に入るようにしましょう。
対策⑥ 寝具の見直し
寝ているときに寒く感じる場合、使っている寝具の保温力が落ちているのかもしれません。
長い期間使用している寝具は、経年劣化でヘタっている可能性もあります。
まだ羽毛ふとんを使用されていない方は、軽くて温かい羽毛ふとんを使用してみるのも良いでしょう。
■まとめ
いかがでしたでしょうか?冬に眠れない原因と対処法について説明させていただきました。
寒い冬はどうしても寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下するものです。だからといって、寝つきが悪いままでは身も心も荒んでしまいます。日々の生活を変えることはなかなか難しいものですが、できることからコツコツと直していくことで、少しでも快適な睡眠がとれるようにしたいものですね。
春の七草

春の七草
お正月も気づけばあっという間にすぎてしまいますね。今年はコロナウイルスの影響もありご自宅で過ごされた方も多いのではないでしょうか。お正月のお酒やご馳走で胃腸も疲れている時期です。体内環境を整えるために1月7日に七草粥を頂いてはいかがでしょうか?
生活環境の変化と負けないカラダ作り

「新型コロナウイルスが私たちに与えた影響」
全世界で猛威を振るっている「新型コロナウイルス」の影響で、私たちの日常生活は大きく変化しました。マスクの着用が当たり前になり、テレワークやオンライン会議が増えるなど人と対面する機会が減っています。また、外出自粛が推奨され、今まで当たり前のように出来ていた家族や友人との食事、旅行なども気を使わなければなりません。先の見えないコロナ渦で大きく環境が変化したことによるストレスなどで、身体や心の不調を訴える人が増加しています。
ここではコロナ渦が心身に与える影響とその対策についてお話します。
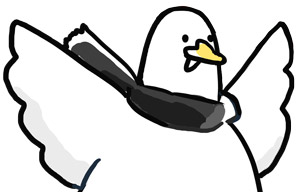 ① 身体への影響
① 身体への影響・コロナ太り
感染対策として在宅ワークやリモート授業を実施する企業や学校が増えました。通勤通学がなくなり、外出自粛に伴って運動をする機会が減ったことで体重が増加してしまう人が多くなっています。・睡眠不足
新型コロナウイルスの感染拡大を防止しながら日常生活を維持する「withコロナ」時代の中で、私たちは以前とは違う新しい生活様式を余儀なくされています。日常生活だけでなく様々な面で変化が起き、多くの人がストレスを感じながら生活するようになりました。
冬の寝室環境を見直して快眠を手に入れる

■理想的な寝室の環境は?
冬時期に、人が気持ちよく眠れる環境は、室温が16℃~19℃、布団の中の温度は32℃くらい、そして湿度は50%~60%です。
室温が16℃よりも低くなると、眠っていても途中で目覚めることが多くなったり、レム睡眠の時間が短くなったりして熟睡ができなくなります。
定期的にしたいお布団のお手入れ

定期的にしたいお布団のお手入れ
今年も大掃除が始まる時期になりました。新年を気持ちよく迎えるために、各ご家庭でお掃除の準備をしだす方もいるでしょう。古くから、年末の大掃除は神様を迎える準備や、厄払いといった意味があります。
朝起きたら風邪を引いている理由

1日のうちで風邪を引きやすい時間帯はいつでしょうか?
埼玉県の歯科医が、来院した706人の患者に対して『風邪の症状に気がつく時間帯』について行った調査によると、「朝起きたとき」が47.5%、「夕方から夜」が29.5%、「昼間」が14%、「夜中」が3.3%、分からないが5.8%でした。
睡眠と記憶の関係性
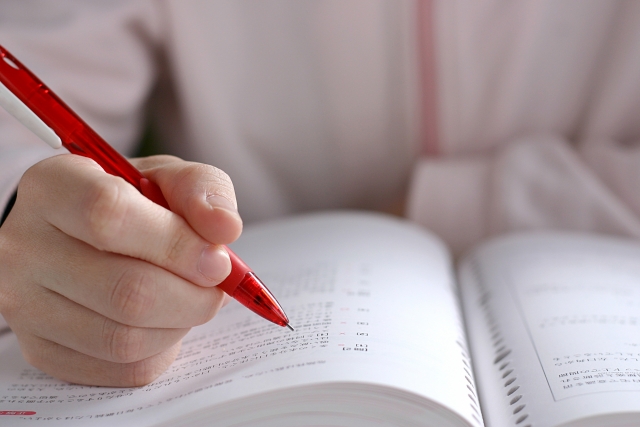
睡眠と記憶の関係性
受験や大切な試験が控えている人も多い時期なのではないでしょうか。ついつい睡眠時間を削って勉強してしまいがちですが、勉強したことを記憶として定着させる為にはしっかり睡眠をとることが効果的です。
睡眠不足の運転は、飲酒運転に匹敵する!?

睡眠不足の運転は、飲酒運転に匹敵する!?
警察庁交通局の調べによると、交通事故で亡くなった人は、昭和45年がピークで16755人いました。しかし去年は3215人と少なくなっています。
しかしこれは、エアバックの装備やヘルメット・シートベルトの装着、それに加えて医療技術の発達などの影響で少なくなったとも考えられます。
電気毛布の適切な使い方
電気毛布の適切な使い方
冬になると布団に入ったときに冷たく感じるのが苦手な人も多いのではないでしょうか。簡単に温まれるという事で電気毛布を使う人も多いと思いますが、正しい使い方などを考えたことはありますか?
ベストな睡眠時間とは?

■理想的な睡眠時間はどれくらい?
8時間睡眠神話とでも言えるかのように、昔は8時間といわれていましたが、最近は人それぞれ必要な睡眠時間は違うというのが一般的です。ただ、平均睡眠時間というのは8時間に近いです。










